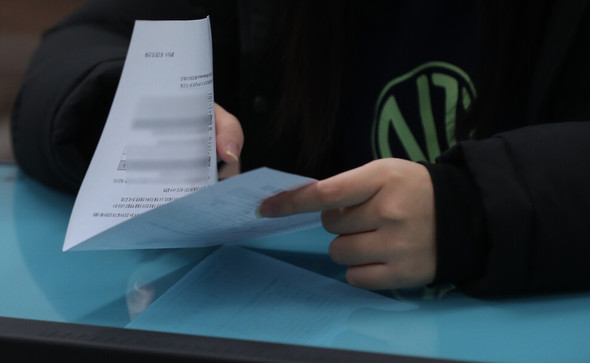
地下鉄に乗って通勤していると、大学名が大きく記されたジャンパーを着た学生たちをよく見かける。中学生たちもスラスラ暗唱するという「大学序列ピラミッド」でいえば、真ん中以上にはなる大学が多かったと思う。2人の子を育てる父親のおせっかいだろうか。そのジャンパーを見ると、たまにこんな風に思うことがある。もしかして地下鉄の同じ車両に「名もない」大学の在学生がいるのではないか。「誇らしく」見せびらかしている自分の大学より序列が上の大学の学生が乗っていたら、委縮してしまうのではないか。
大学ジャンパーは、単なるファッションとは考えがたい。韓国社会の根強い序列主義が投影された「区別付け」文化の一つと解釈した方が、より現実に合っているように思える。絶えず並ばせ、区別をつける社会では、優越感よりも挫折を感じる人の方がはるかに多くならざるを得ない。下に行くほど広くなるのがピラミッドの属性だ。
もちろん、学生たちの「承認欲求」が全く理解できないわけではない。熾烈(しれつ)な競争を勝ち抜いた人たちにのみそのジャンパーを着る資格が与えられるわけだから、「私、この大学に通っているんです」と自慢したい気持ちがないはずがない。その「看板」を手に入れるためにどれほど苦労したかを考えると、気の毒な気さえする。もしかしたら、彼らは幼い頃から競争を内面化するよう強要してきた社会システムの被害者かもしれない。最近の若い世代の寒々とした能力主義と公正さに対する強迫観念を非難する声が多いが、それもまた競争中毒社会の悲しい自画像ではないかとも思う。
大学の序列をつける上で、大学修学能力試験(修能)は圧倒的な権威を誇る。大学入試シーズンが終われば、その年の入試結果(別名「入結」)をめぐって入試サイトなどでは「我々の方が上だ」、「どの大学がどこを追い抜いた」などと、ひとしきり「学閥バトル」が繰り広げられたりもするが、「入結」の核心の指標こそが修能の点数だ。「大学序列遊び」を事とする人々を指す「学歴フーリガン」という言葉が出てきて久しい。
修能がこのように「序列の神業」を発揮できるのは、相対評価だからだ。全国の学生たちを1位から最下位まで並べることができるわけだから、これほどの物差しは他にない。相対評価体制では、すべての構成員が同じように努力したとしても、細かく順位がつけられる。誰もが果てのない競争へと追いやられるが、結局はごく一部を除いた大多数を敗者にする意地悪なシステムだ。
今年の修能をちょうど1週間後に控えた先月10日、「大学入試の相対評価は違憲」だという違憲訴訟が起こされた。修能と高校の内申の相対評価は「殺人的な競争」を誘発するため、憲法の保障する幸福追求権、健康権、教育権などを侵害するとの趣旨だ。教育運動団体「私教育の心配のない世の中」が主導したこの違憲訴訟に対しては、96人の弁護士が「違憲宣言文」を通じて支持を表明している。「誰かを踏みにじって収めた勝利の強要、たった1%を選び出すための評価は、その目的が正当でないだけでなく、自己破壊的で非教育的で反人間的だ」。熾烈な競争を勝ち抜いて、相対評価体制において「勝者」となった弁護士たちが、100人近く支持宣言をしたということに驚く。
保守陣営は相変わらずもっと多くの競争が必要だと叫んでいるが、韓国は競争が足りないからではなく、多すぎるからこそ数多くの病弊を生みだしているのだ。光州科学技術院のキム・ヒサム教授が2017年に韓国、中国、日本、米国の4カ国の大学生に、自国の高等学校がどんなイメージに最も近いと考えるかを調査したところ、韓国の大学生の81%が「死活をかけた戦場」と答えた。中国(42%)、米国(40%)、日本(13.8%)に比べて圧倒的に高い。このような学校において、弱者に対する配慮や共感、連帯のような共同体的心性を育てるのは不可能に近い。英国オックスフォード大学のジョナサン・ガシュニー教授は「週刊東亜」とのインタビューで、韓国の入試競争を「冷戦時代の果てしない軍拡競争」に例えている。
私たちは相対評価を当然のことと考えているが、先進国に属する国々に入試で相対評価を採用している国は見当たらない。一定の資格を備えれば大学に入学する機会を与えてくれるというのが、より「グローバルスタンダード」に近い。だが、そのような国々の競争力が韓国より劣るという話は聞いたことがない。
相対評価は単に選抜システムとして有用であるにすぎず、「学びを通じた成長」という教育の本領とはかけ離れている。きめ細かな選抜のためには避けられないという論理は強固に存在するが、本末転倒であるばかりだ。もちろん、高校の内申を絶対評価に変えるためには、必ず取り除くべき障害物がある。「学校の多様化」という美名の下に幾重にも序列化した高校体制だ。特別目的高校や自律型私立高校などを維持したまま絶対評価を導入すれば、それらの学校の「入試特権」ばかりを強化することになるのは火を見るより明らかだ。高校進学段階でも入試競争が激化するという副作用が伴わざるを得ない。
競争を宿命と考える韓国社会においては、保守的な憲法裁が相対評価を違憲と宣言する可能性は低い。しかし訴訟を通じて、他者を蹴落として生き延びるという競争をあおる相対評価の弊害を公論化するだけでも、その意味は決して小さくない。慣れすぎて問題点そのものが認識できない状況においては、より良い代案を考える必要性も感じることができないからだ。
米国の教育心理学者アルフィ・コーンは著書『競争社会をこえて』で、競争の本質は、1人の成功のためにはその他の人々は失敗しなければならないという「相互排他的な」目標達成のあり方にあると指摘した。今年の入試が終われば、またどれほど多くの「失敗者」が挫折を体験することになるか分からない。入学もしないうちに隠れ浪人を決心する人も多いだろう。そばで見守る親にとっても並大抵のことではないだろう。このように皆を不幸にするシステムを、金科玉条のようにありがたがらなければならない理由などあるのだろうか。

イ・ジョンギュ|論説委員 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
訳D.K

